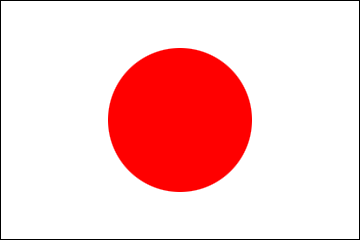戸籍・国籍関係届
令和7年9月15日
戸籍法の改正により、2025年5月から戸籍の氏名にフリガナが記載されることに伴い、2026年5月25日までにフリガナの届出が必要になります(海外在住の方は、期間経過後でも日本で届出をすることができます)。
詳しくは外務省ホームページ( https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/pagew_000001_01529.html )をご確認ください。
(各届出様式はこちら https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html )
※各種届の提出前に当館メールアドレスまで書類の送付をお願いします。
1 出生届
日本国外で出生した場合、出生届は戸籍法により、出生の日から3ヶ月以内 に届けることと定められています。出生時に日本国籍以外の国籍を併せ取得する子(例えば、父又は母が外国籍者である、若しくは生地主義国で生まれた場合等)は、日本国籍を留保する意思を表示(出生届に署名)しなければ、出生の時にさかのぼって日本の国籍を失うこととなりますのでご注意下さい。
(1) 届出に必要な書類
○ 出生届(用紙を印刷できない場合は、当館に備え付けてあります。):2通
○ 外国官公署発行の出生登録証明書又は医師作成の出生証明書の原本:2通※
○ 同和訳文(届出人が作成したもの。文の最後に翻訳者がご署名ください。):2通※
○ 出産した病院が作成する病院名及び住所が確認できる書類:2通※
○ 父母の旅券
※出生届以外の書類について、1通は原本である必要がありますが、他は写しでも差し支えありません。
(2)留意事項
出生届提出後、通常1~2ヶ月で日本の戸籍に出生の事実が記載されます。なお、お子様が戸籍に記載されたか否かについては御両親が本籍地に直接確認して下さい。日本旅券の取得に当たっては、お子様の戸籍謄(抄)本を日本から取り寄せる必要があります。
また、直接本籍地役場に届出することも可能です。その場合は、予め本籍地役場に必要書類をご確認下さい。
2 婚姻届
婚姻届は、戸籍法により婚姻成立の日から3ヶ月以内に届出なければなりません。3ヶ月を超えて届け出る場合は、遅延理由書(署名が必要)を婚姻届と同じ通数作成して下さい。
(1)日本人同士の婚姻
当事者双方が日本法で定める婚姻の実質的要件(婚姻年齢、重婚でないこと等)を満たす場合には、届出のみで婚姻が成立します。(婚姻届に当事者双方及び成年の証人2名の署名(押印は任意)が必要です。)
(ア)届出に必要な書類
○ 婚姻届(用紙を印刷できない場合は、当館に備え付けてあります。):2通
○ 婚姻証明書(挙行地の方式によるとき):2通※
○ 同和訳文 (届出人が作成したもの。文の最後に翻訳者がご署名ください。):2通※
※婚姻届以外の書類について、1通は原本である必要がありますが、他は写しでも差し支えありません。
(2)日本人と外国人の婚姻
外国の法律に基づいて外国人と婚姻された場合は、婚姻成立の日から3ヶ月以内に当館に届け出てください。
(外国の法律に基づいた婚姻が成立する前に日本方式により外国人と婚姻する場合は、本籍地のある役所に直接ご連絡ください。)
(ア)届出に必要な書類
○ 婚姻届(用紙を印刷できない場合は、当館に備え付けてあります。):2通
○ 婚姻証明書( Certified Copy of Marriage Certificate):2通※
○ 同和訳文 (届出人が作成したもの。文の最後に翻訳者がご署名ください。):2通※
○ 外国人配偶者の国籍を証明する書類:2通※
○ 同和訳文:2通※
○ 双方の旅券
※婚姻届以外の書類について、1通は原本である必要がありますが、他は写しでも差し支えありません。
(イ)留意事項
戸籍上の氏を外国人配偶者の氏に変更(日本の氏に外国の氏を付け加える形での変更は家庭裁判所の許可が必要です)する方は、婚姻成立の日から6ヶ月以内であれば、家庭裁判所の許可なしで変更可能です。届出用紙をご希望の方はお申し出下さい。
3 不受理申出制度
不受理申出制度は、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。不受理申出後、当該申出に係る届出があった場合、申出をした本人が窓口に来たことが確認できなかったときは当該届出を受理しません。
(1)日本人が不受理申出を行う場合
(ア)対象となる届出
認知届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届
(イ)申出ができる人
(A)認知届…認知者(父)
(B)婚姻届、離婚届…夫および妻
(C)養子縁組届、養子離縁届…養親および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
(ウ)届出方法
申出人本人が窓口に直接届け出ます(郵送することは原則としてできません)。
(エ)届出に必要な書類
○ 不受理申出書(用紙を印刷できない場合は、当館に備え付けてあります。):2通
認知届不受理申出書
婚姻届不受理申出書
離婚届不受理申出書
養子縁組届不受理申出書
養子離縁届不受理申出書
○ 申出人の本人確認ができるもの(パスポート等の官公署が発行した顔写真入りの本人確認資料)
○ 法定代理人であることを証明する書類(15歳未満の者について申出を行う場合):2通(原本1通、写し1通)
(オ)留意事項
この不受理申出をしていても、外国法により成立した、または裁判により確定したことによる当該届出(報告的届出)については受理されます。
(2)外国人が不受理申出を行う場合
日本国内であれば外国人の方も日本人を相手方とする不受理申出をすることはできますが、在外公館では、外国人の方から不受理申出を受け付けることはできません。
したがいまして、外国人の方は、原則として、日本の市区町村役場の窓口に出頭して不受理申出を行う必要がありますが、自ら出頭できない事情がある場合は、書面の送付により申出できる可能性もありますので、本邦の市区町村役場にお問い合わせ下さい。
4 国籍選択届
外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、20歳に達するまでに(18歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)、どちらかの国籍を選択する必要があります (国籍法14条1項)。 選択しない場合は、日本の国籍を失うことがありますので注意してください。
(注)ただし、令和4年(2022年)4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足ります。
(注)令和4年(2022年)4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。
(注)以上の期限を徒過してしまった場合であっても、いずれかの国籍を選択する必要があります。
(1)国籍の選択をしなければならない人
(ア)日本人父母の間に生地主義を採る国(米国、カナダ、ブラジル等)で生まれた子。
(イ)父母両系血統主義を採る国(ドイツ、中国、フィリピン、フランス等)の国籍を有する父(又は母)と日本人母(又は父)との間に生まれた子。
(ウ)父系血統主義を採る国(バーレーン、インドネシア等)の国籍を有する父と日本人母との間に生まれた子。(なお、父が日本人で、母がバーレーン人又はインドネシア人の場合は、お子さんはそれら母の国の国籍を取得しませんので、日本国籍を留保する必要はありません)
(エ)外国人(例えば、カナダ)父からの認知、外国人(例えば、イタリア)との養子縁組、外国人(例えば、イラン)との婚姻などによって外国の国籍を取得した人 。
(オ)帰化又は国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している人 。
(2)国籍の選択の方法
国籍の選択は、自己の意思に基づいて、次のいずれかの方法により行って下さい。なお,下記(イ)(A)の国籍離脱届以外は郵送による届出も可能です。
(ア)日本国籍を選択する場合
(A)当該外国の国籍を離脱する方法
当該外国の法令により、その国の国籍を離脱した場合は、離脱を証明する書面を添付して在外公館又は本邦の市区町村役場に外国国籍喪失届を提出して下さい。
離脱の手続きについては、当該外国の関係機関に相談して下さい。
(B)日本の国籍の選択を宣言する方法
戸籍謄本を添付して、在外公館又は本邦の市区町村役場に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届を提出して下さい。
(イ)外国の国籍を選択する場合
(A)日本の国籍を離脱する方法
住所地を管轄する在外公館又は本邦法務局・地方法務局に戸籍謄本、住所を証明する書面、外国国籍を有することを証する書面を添付して、国籍離脱届を提出して下さい。
なお、この届は日本国籍を離脱する本人(15歳未満である場合は、法定代理人)が自ら在外公館又は本邦法務局・地方法務局に出向く必要がありますので、注意して下さい。
(B)外国の国籍を選択する方法
当該外国の法令により、その国の国籍を選択した場合は、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付して、在外公館又は本邦の市区町村役場に国籍喪失届を提出して下さい。
なお、国籍法では選択期限が設けられていますが、この期限を過ぎても引き続き選択義務はありますので、ご留意願います。
(3)日本国籍の喪失にご注意下さい
海外に在留する日本人は、一定の行為の結果、日本国籍を喪失してしまうことを自ら理解しない内に、自動的に日本国籍を失ってしまうことがありますのでご注意下さい。
たとえば、
外国に帰化(外国の国籍を取得)した場合
外国人と結婚して外国籍を取得した場合
外国で重国籍の子が出生したときに、国籍留保届をしなかった場合
法務大臣から催告を受けたにもかかわらず、国籍選択届をしなかった場合
等が例としてあげられますが、個々の具体的事情によって結果が異なりますので、詳細については、当館領事窓口にお問い合わせ下さい。
詳しくは外務省ホームページ( https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/pagew_000001_01529.html )をご確認ください。
(各届出様式はこちら https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html )
※各種届の提出前に当館メールアドレスまで書類の送付をお願いします。
1 出生届
日本国外で出生した場合、出生届は戸籍法により、出生の日から3ヶ月以内 に届けることと定められています。出生時に日本国籍以外の国籍を併せ取得する子(例えば、父又は母が外国籍者である、若しくは生地主義国で生まれた場合等)は、日本国籍を留保する意思を表示(出生届に署名)しなければ、出生の時にさかのぼって日本の国籍を失うこととなりますのでご注意下さい。
(1) 届出に必要な書類
○ 出生届(用紙を印刷できない場合は、当館に備え付けてあります。):2通
○ 外国官公署発行の出生登録証明書又は医師作成の出生証明書の原本:2通※
○ 同和訳文(届出人が作成したもの。文の最後に翻訳者がご署名ください。):2通※
○ 出産した病院が作成する病院名及び住所が確認できる書類:2通※
○ 父母の旅券
※出生届以外の書類について、1通は原本である必要がありますが、他は写しでも差し支えありません。
(2)留意事項
出生届提出後、通常1~2ヶ月で日本の戸籍に出生の事実が記載されます。なお、お子様が戸籍に記載されたか否かについては御両親が本籍地に直接確認して下さい。日本旅券の取得に当たっては、お子様の戸籍謄(抄)本を日本から取り寄せる必要があります。
また、直接本籍地役場に届出することも可能です。その場合は、予め本籍地役場に必要書類をご確認下さい。
2 婚姻届
婚姻届は、戸籍法により婚姻成立の日から3ヶ月以内に届出なければなりません。3ヶ月を超えて届け出る場合は、遅延理由書(署名が必要)を婚姻届と同じ通数作成して下さい。
(1)日本人同士の婚姻
当事者双方が日本法で定める婚姻の実質的要件(婚姻年齢、重婚でないこと等)を満たす場合には、届出のみで婚姻が成立します。(婚姻届に当事者双方及び成年の証人2名の署名(押印は任意)が必要です。)
(ア)届出に必要な書類
○ 婚姻届(用紙を印刷できない場合は、当館に備え付けてあります。):2通
○ 婚姻証明書(挙行地の方式によるとき):2通※
○ 同和訳文 (届出人が作成したもの。文の最後に翻訳者がご署名ください。):2通※
※婚姻届以外の書類について、1通は原本である必要がありますが、他は写しでも差し支えありません。
(2)日本人と外国人の婚姻
外国の法律に基づいて外国人と婚姻された場合は、婚姻成立の日から3ヶ月以内に当館に届け出てください。
(外国の法律に基づいた婚姻が成立する前に日本方式により外国人と婚姻する場合は、本籍地のある役所に直接ご連絡ください。)
(ア)届出に必要な書類
○ 婚姻届(用紙を印刷できない場合は、当館に備え付けてあります。):2通
○ 婚姻証明書( Certified Copy of Marriage Certificate):2通※
○ 同和訳文 (届出人が作成したもの。文の最後に翻訳者がご署名ください。):2通※
○ 外国人配偶者の国籍を証明する書類:2通※
○ 同和訳文:2通※
○ 双方の旅券
※婚姻届以外の書類について、1通は原本である必要がありますが、他は写しでも差し支えありません。
(イ)留意事項
戸籍上の氏を外国人配偶者の氏に変更(日本の氏に外国の氏を付け加える形での変更は家庭裁判所の許可が必要です)する方は、婚姻成立の日から6ヶ月以内であれば、家庭裁判所の許可なしで変更可能です。届出用紙をご希望の方はお申し出下さい。
3 不受理申出制度
不受理申出制度は、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。不受理申出後、当該申出に係る届出があった場合、申出をした本人が窓口に来たことが確認できなかったときは当該届出を受理しません。
(1)日本人が不受理申出を行う場合
(ア)対象となる届出
認知届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届
(イ)申出ができる人
(A)認知届…認知者(父)
(B)婚姻届、離婚届…夫および妻
(C)養子縁組届、養子離縁届…養親および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
(ウ)届出方法
申出人本人が窓口に直接届け出ます(郵送することは原則としてできません)。
(エ)届出に必要な書類
○ 不受理申出書(用紙を印刷できない場合は、当館に備え付けてあります。):2通
認知届不受理申出書
婚姻届不受理申出書
離婚届不受理申出書
養子縁組届不受理申出書
養子離縁届不受理申出書
○ 申出人の本人確認ができるもの(パスポート等の官公署が発行した顔写真入りの本人確認資料)
○ 法定代理人であることを証明する書類(15歳未満の者について申出を行う場合):2通(原本1通、写し1通)
(オ)留意事項
この不受理申出をしていても、外国法により成立した、または裁判により確定したことによる当該届出(報告的届出)については受理されます。
(2)外国人が不受理申出を行う場合
日本国内であれば外国人の方も日本人を相手方とする不受理申出をすることはできますが、在外公館では、外国人の方から不受理申出を受け付けることはできません。
したがいまして、外国人の方は、原則として、日本の市区町村役場の窓口に出頭して不受理申出を行う必要がありますが、自ら出頭できない事情がある場合は、書面の送付により申出できる可能性もありますので、本邦の市区町村役場にお問い合わせ下さい。
4 国籍選択届
外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、20歳に達するまでに(18歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)、どちらかの国籍を選択する必要があります (国籍法14条1項)。 選択しない場合は、日本の国籍を失うことがありますので注意してください。
(注)ただし、令和4年(2022年)4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足ります。
(注)令和4年(2022年)4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。
(注)以上の期限を徒過してしまった場合であっても、いずれかの国籍を選択する必要があります。
(1)国籍の選択をしなければならない人
(ア)日本人父母の間に生地主義を採る国(米国、カナダ、ブラジル等)で生まれた子。
(イ)父母両系血統主義を採る国(ドイツ、中国、フィリピン、フランス等)の国籍を有する父(又は母)と日本人母(又は父)との間に生まれた子。
(ウ)父系血統主義を採る国(バーレーン、インドネシア等)の国籍を有する父と日本人母との間に生まれた子。(なお、父が日本人で、母がバーレーン人又はインドネシア人の場合は、お子さんはそれら母の国の国籍を取得しませんので、日本国籍を留保する必要はありません)
(エ)外国人(例えば、カナダ)父からの認知、外国人(例えば、イタリア)との養子縁組、外国人(例えば、イラン)との婚姻などによって外国の国籍を取得した人 。
(オ)帰化又は国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している人 。
(2)国籍の選択の方法
国籍の選択は、自己の意思に基づいて、次のいずれかの方法により行って下さい。なお,下記(イ)(A)の国籍離脱届以外は郵送による届出も可能です。
(ア)日本国籍を選択する場合
(A)当該外国の国籍を離脱する方法
当該外国の法令により、その国の国籍を離脱した場合は、離脱を証明する書面を添付して在外公館又は本邦の市区町村役場に外国国籍喪失届を提出して下さい。
離脱の手続きについては、当該外国の関係機関に相談して下さい。
(B)日本の国籍の選択を宣言する方法
戸籍謄本を添付して、在外公館又は本邦の市区町村役場に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届を提出して下さい。
(イ)外国の国籍を選択する場合
(A)日本の国籍を離脱する方法
住所地を管轄する在外公館又は本邦法務局・地方法務局に戸籍謄本、住所を証明する書面、外国国籍を有することを証する書面を添付して、国籍離脱届を提出して下さい。
なお、この届は日本国籍を離脱する本人(15歳未満である場合は、法定代理人)が自ら在外公館又は本邦法務局・地方法務局に出向く必要がありますので、注意して下さい。
(B)外国の国籍を選択する方法
当該外国の法令により、その国の国籍を選択した場合は、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付して、在外公館又は本邦の市区町村役場に国籍喪失届を提出して下さい。
なお、国籍法では選択期限が設けられていますが、この期限を過ぎても引き続き選択義務はありますので、ご留意願います。
(3)日本国籍の喪失にご注意下さい
海外に在留する日本人は、一定の行為の結果、日本国籍を喪失してしまうことを自ら理解しない内に、自動的に日本国籍を失ってしまうことがありますのでご注意下さい。
たとえば、
外国に帰化(外国の国籍を取得)した場合
外国人と結婚して外国籍を取得した場合
外国で重国籍の子が出生したときに、国籍留保届をしなかった場合
法務大臣から催告を受けたにもかかわらず、国籍選択届をしなかった場合
等が例としてあげられますが、個々の具体的事情によって結果が異なりますので、詳細については、当館領事窓口にお問い合わせ下さい。